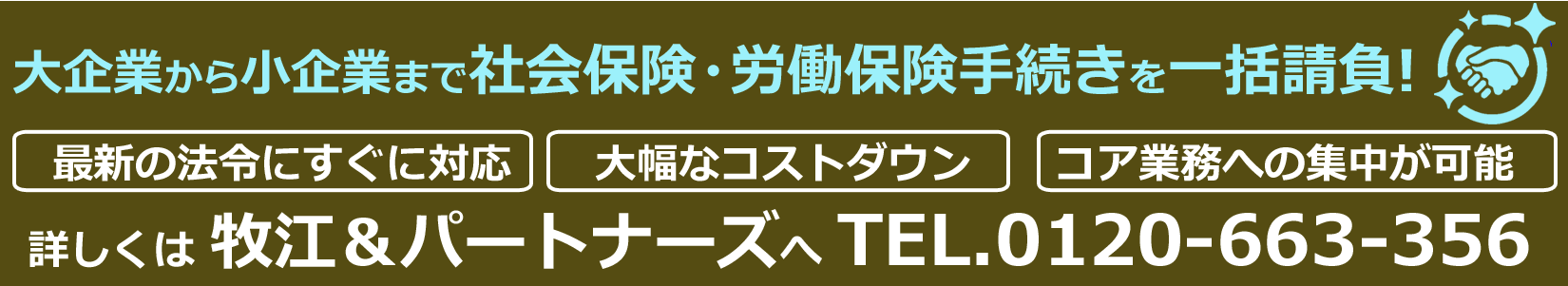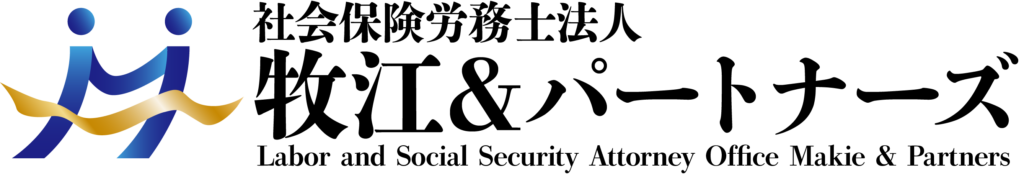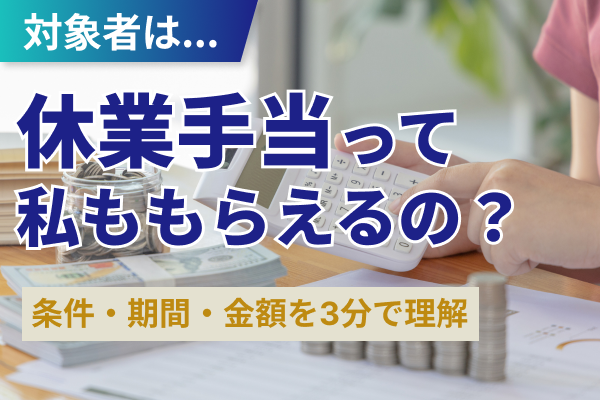
やむを得ない理由で会社を長期間休むことになった、もしくは会社都合でやむなく休業させられた、という人は案外少なくありません。その間、休業手当はもらえるのか不安に思う人も多いでしょう。
休業手当は労働基準法で定められた制度で、一定の条件を満たせば平均賃金の60%以上を受け取ることができます。
この記事では、休業手当の支給条件や計算方法、雇用形態別の取り扱い、他の制度との違いなど、知っておくべきポイントを3分で理解できるよう解説します。
- 休業手当の定義と支給条件(会社都合の休業が対象)
- 平均賃金の60%以上という支給金額の計算方法
- 派遣・パート・アルバイトなど雇用形態別の取り扱い
- 休業手当と傷病手当金・休業補償などの違い
- 休業手当の課税と社会保険料の扱い
- よくある質問と具体的なシミュレーション
休業手当とは?もらえる条件を3分で理解!
休業手当は、会社の都合で従業員を休ませる場合に支払われる手当です。労働基準法第26条には以下のように記されています。
|
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない |
つまり、会社側の責任で休業する場合は、従業員は休業期間中も平均賃金の60%以上を受け取る権利があるということです。休業手当は「賃金」として扱われるため、通常の給与と同様に所得税や社会保険料の対象となります。
ここからは、休業手当の定義や具体的な支給条件について確認しましょう。
休業手当がもらえるのは「会社都合の休業」
休業手当の支給対象となるのは、会社側の責任による休業のみです。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 経営不振や資金難による操業停止
- 原材料不足や設備故障による生産停止
- 取引先からの発注減少による休業
- 内定者への自宅待機命令
- 予告なしの解雇における予告期間中の休業
- 会社判断による営業時間短縮や店舗休業
一方、労働者自身の病気やケガ、天災など不可抗力による休業は対象外となります。これらについては、休業手当とは別の制度が敷かれています。詳しくは「休業手当の支給条件|会社都合・病気・うつ病など状況別に解説」で確認しましょう。
休業手当の金額|平均賃金の60%以上
休業手当の金額は、労働基準法により平均賃金の60%以上と定められています。平均賃金は、休業が発生した日の直前3か月間に支払われた給料の総額を、その期間の総日数(暦日数)で割って算出します。
例えば、直前3か月の賃金総額が75万円、総日数が92日、休業日数が10日の場合配下のような計算式になります。
| 項目 | 計算式・結果 |
| 平均賃金 | 750,000円 ÷ 92日 = 8,152円 |
| 休業手当の日額 | 8,152円 × 60% = 4,891円 |
| 休業手当の合計 | 4,891円 × 10日 = 48,910円 |
会社は60%を上回る金額を支払うこともでき、就業規則等で70%や100%と定めている企業もあります。
平均賃金の計算において、賃金総額に含まれるものと含まれないものがあります。正確な金額を算出するために、以下の区分を理解しておきましょう。
| 区分 | 具体例 |
| 含まれるもの | 基本給、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役職手当、職務手当、深夜手当、休日出勤手当など |
| 含まれないもの | 結婚祝金・出産祝金などの臨時の賃金、賞与(3か月を超える期間ごとに支払われるもの)、退職金、現物給与(通常は含まれるが計算が複雑) |
正確な金額を知りたい場合は、給与明細の過去3か月分を確認し、賞与や臨時の給付を除いた合計額を計算しましょう。
休業手当の支給期間|会社都合の休業が続く期間
休業手当の支給期間について、労働基準法には特に上限の定めはありません。会社都合の休業が続く限り、休業手当の支払い義務は継続します。
ただし、長期間にわたる休業の場合は、最終的に解雇や退職につながる可能性もあります。その場合は、失業給付など別の制度に移行することになります。支給開始日は休業開始日からで、通常は次の給与支払日に支払われます。
休業手当の支給条件|会社都合・病気・うつ病など状況別に解説
休業の理由によって、休業手当の支給対象となるかどうかが変わります。ここでは、よくある状況別に支給条件を詳しく解説します。会社都合かどうかが判断の基準となり、労働者側の事情や不可抗力による休業は原則として対象外です。
ただし、一見すると会社都合ではないように見えても、実際には支給対象となるケースもあります。以下で詳しく確認してみましょう。
病気やうつ病による休業は対象外|傷病手当金を利用
労働者自身の病気やケガ、うつ病などのメンタルヘルス不調による休業は、「使用者の責に帰すべき事由」には該当しないため、休業手当の支給対象外となります。
この場合は、健康保険の「傷病手当金」を利用することができます。傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休んだときに、最長1年6か月間、標準報酬日額の3分の2相当額が支給される制度です。
支給開始日から3日間の待期期間が必要ですが、その後は連続した期間だけでなく、断続的な休業でも支給対象となります。
- 業務外の病気やケガで療養中であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間の待期期間があること
- 給与の支払いがないこと(一部支給の場合は差額支給)
台風・大雪などの天災による休業も原則対象外
台風や大雪、地震などの自然災害による休業は、原則として「不可抗力」と判断され、休業手当の支給義務はありません。不可抗力と認められるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
| 要件 | 内容 |
| 外部性 | 原因が事業の外部より発生した事故であること |
| 回避不可能性 | 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること |
ただし、天災が発生しても、会社の判断で休業させた場合は休業手当の支払いが必要となることがあります。
例えば、交通機関は動いているのに、客足が減少することを見込んで店舗を休業した場合などは、会社都合と判断される可能性があります。2025年10月現在では、台風などの気象災害時の取り扱いについては、各企業の就業規則や労働契約の内容によって異なる場合があるため、気になった場合には勤め先に確認してみましょう。
倒産・リストラによる休業の扱い
会社の倒産やリストラによる休業は、明確な会社都合の休業として、休業手当の支給対象となります。特に、解雇予告なしに即時解雇する場合は、解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)の支払いが必要です。
また、会社が倒産して休業手当が支払われない場合は、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する「未払賃金立替払制度」を利用できる可能性があります。この制度では、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金(退職金を含む)の80%が立替払されます。
雇用形態別の休業手当|派遣・パート・アルバイトも対象?
休業手当は、雇用形態に関係なくすべての労働者が対象となります。正社員だけでなく、派遣社員、パート、アルバイト、契約社員など、労働基準法上の「労働者」であれば、休業手当を受け取る権利があります。
ただし、雇用形態によって計算方法や支払い主体が異なる場合があります。ここでは、各雇用形態における休業手当の取り扱いを詳しく解説します。
派遣社員の場合|派遣元会社が支払う
派遣社員の場合、休業手当を支払う義務を負うのは派遣元会社です。
派遣先の都合で休業が発生した場合でも、雇用契約は派遣元会社と結んでいるため、派遣元が休業手当を支払います。
例えば、派遣先企業が経営不振で休業を指示した場合、派遣社員は派遣元会社に対して休業手当を請求します。派遣元会社は派遣先に対して補償を求めることはできますが、労働者への支払い義務は派遣元にあります。派遣契約期間中であれば、派遣先の都合による休業でも平均賃金の60%以上を受け取る権利があります。
- 支払い義務者は派遣元会社
- 派遣先の都合による休業も対象
- 派遣契約期間中の休業が対象
- 登録型派遣の場合、派遣契約がない期間は対象外
パート・アルバイトの場合|短時間勤務でももらえる
パートやアルバイトも、労働基準法上の労働者として休業手当の支給対象となります。週の勤務時間が短い場合や、勤務日数が少ない場合でも、会社都合の休業であれば休業手当を受け取ることができます。
計算方法は正社員と同じで、直前3か月間の賃金総額を総日数で割って平均賃金を算出し、その60%以上が支給されます。
ただし、時給制や日給制の場合は最低保障額の規定があり、「直前3か月の賃金総額÷直前3か月の労働日数×0.6」という計算式による金額が、通常の計算方法による平均賃金を上回る場合は、最低保障額が適用されます。
| 項目 | 通常の計算 | 最低保障額 |
| 計算式 | 賃金総額 ÷ 総日数 | (賃金総額 ÷ 労働日数)× 0.6 |
| 例:賃金総額18万円/総日数92日、労働日数40日 | 1,957円 | 2,700円 |
| 採用される金額 | 2,700円(高い方) | |
この例では、最低保障額の方が高いため、平均賃金は2,700円となり、休業手当の日額は1,620円以上となります。
契約社員・嘱託社員の場合|有期雇用でも対象になる
契約社員や嘱託社員も、労働基準法上の労働者として休業手当の対象となります。有期雇用契約であっても、契約期間中の会社都合による休業には休業手当の支払いが必要です。
契約更新時期に休業が発生した場合は、契約更新の有無によって取り扱いが異なります。契約が更新されている場合は、新しい契約期間中の休業として休業手当の対象となります。契約が更新されず、契約期間満了となった場合は、雇用関係が終了するため、休業手当ではなく失業給付の対象となります。
日雇い・短期バイトの場合|労働契約内容による
日雇いや短期アルバイトの場合、労働契約の内容によって判断が異なります。特定の日に働く約束がされていて、会社都合でその日の労働がキャンセルされた場合は、休業手当の支給対象となる可能性があります。
ただし、「日々雇い入れられる者」として、その日ごとに労働契約が成立・終了する形態の場合は、そもそも休業という概念が発生しないため、休業手当の対象外となることが一般的です。日雇い派遣の場合も、派遣契約の内容によって判断されますが、原則として派遣元会社が支払い義務を負います。
休業手当の税金と社会保険|課税される?厚生年金はどうなる?
休業手当は「賃金」として扱われるため、通常の給与と同様に税金や社会保険料の対象となります。一方、休業補償(労災保険からの給付)や傷病手当金(健康保険からの給付)は非課税となり、取り扱いが異なります。
ここでは、休業手当にかかる税金と社会保険料について詳しく解説します。休業期間中も継続して負担する必要がある項目もあるため、正確に理解しておくことが重要です。
休業手当は課税対象|所得税・住民税がかかる
休業手当は給与所得として課税されます。所得税は源泉徴収され、住民税も通常どおり課税対象となります。年末調整や確定申告でも、休業手当は給与収入として計上します。
ただし、休業手当は平均賃金の60%程度であるため、通常の給与より低い金額となります。その結果、源泉徴収される所得税額も少なくなり、年間の所得税額が減少する可能性があります。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、休業した年の翌年の住民税が減少することになります。
| 税金の種類 | 課税の有無 | 備考 |
| 所得税 | 課税対象 | 源泉徴収される |
| 住民税 | 課税対象 | 前年所得に基づき課税 |
社会保険料(健康保険・厚生年金)の扱い
休業手当からも、健康保険料と厚生年金保険料は通常どおり控除されます。休業期間中も被保険者資格は継続しているため、社会保険料の支払い義務は変わりません。
社会保険料は、標準報酬月額に基づいて計算されます。短期間の休業であれば標準報酬月額は変更されませんが、休業が長期間にわたり、報酬が大幅に減少した場合は、標準報酬月額が変更される可能性があります。標準報酬月額が下がれば、社会保険料の負担も軽減されますが、将来受け取る年金額にも影響します。
- 健康保険料・厚生年金保険料は通常どおり徴収される
- 休業手当から控除される(労使折半)
- 長期休業の場合、標準報酬月額が変更される可能性がある
- 育児休業中のような保険料免除制度は休業手当にはない
雇用保険料の扱い
雇用保険料も、休業手当から通常どおり控除されます。雇用保険料は実際に支払われた賃金に対して計算されるため、休業手当の額に応じた保険料が徴収されます。2025年10月現在の一般の事業の雇用保険料率は、労働者負担分が0.55%、事業主負担分が0.95%となっています。
休業手当が通常の給与より少ない場合、雇用保険料の負担額も減少します。ただし、雇用保険の被保険者資格は継続しているため、将来失業した際の失業給付の算定基礎には含まれます。
休業中の年金・保険への影響
休業期間中も厚生年金保険料を支払い続けるため、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されます。ただし、休業手当の額が通常の給与より少ない場合、標準報酬月額が下がる可能性があり、その結果、将来の年金額に影響する可能性があります。
健康保険についても、休業期間中は通常どおり保険給付を受けることができます。医療機関での受診や、出産育児一時金、高額療養費などの給付は変わらず受けられます。短期間の休業であれば、年金や保険への実質的な影響は限定的です。
休業手当と他の制度の違い|休業補償・傷病手当金・有給休暇
休業に関連する制度は複数存在し、それぞれ支給条件や金額が異なります。休業手当、休業補償、傷病手当金、有給休暇など、似た名称の制度が多いため混乱しやすいですが、適用される状況を正しく理解することで、自分に最も有利な制度を選択できます。
ここでは、主な休業関連制度との違いを詳しく解説します。
休業手当と休業補償の違い|労災かどうかが判断基準
休業手当と休業補償は、名称が似ていますが全く異なる制度です。最も大きな違いは、休業の原因が業務に起因するかどうかです。
| 項目 | 休業手当 | 休業補償 |
| 対象 | 会社都合の休業 | 業務上の負傷・疾病による休業 |
| 支給額 | 平均賃金の60%以上 | 給付基礎日額の60%+特別支給金20%(合計80%) |
| 支払者 | 使用者(会社) | 労災保険 |
| 課税 | 課税対象 | 非課税 |
| 待期期間 | なし | 3日間(会社が休業補償) |
| 根拠法 | 労働基準法第26条 | 労働基準法第76条+労災保険法 |
休業補償は、業務中や通勤中の事故によるケガや病気で働けなくなった場合に、労災保険から支給されます。給付額は休業手当より高く、非課税であることも大きなメリットです。業務上の災害による休業の場合は、必ず休業補償を申請しましょう。
休業手当と傷病手当金の違い|病気・ケガの場合は傷病手当金
傷病手当金は、健康保険から支給される給付金で、業務外の病気やケガで働けない場合に利用できます。休業手当は会社都合の休業が対象であるのに対し、傷病手当金は労働者自身の健康上の理由による休業が対象です。
| 項目 | 休業手当 | 傷病手当金 |
| 対象 | 会社都合の休業 | 業務外の病気・ケガによる休業 |
| 支給額 | 平均賃金の60%以上 | 標準報酬日額の3分の2 |
| 支払者 | 使用者(会社) | 健康保険 |
| 課税 | 課税対象 | 非課税 |
| 待期期間 | なし | 連続3日間 |
| 支給期間 | 制限なし | 最長1年6か月 |
傷病手当金は、連続する3日間の待期期間の後、4日目から支給が開始されます。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月間です。病気やケガで長期間働けない場合は、傷病手当金が重要な収入源となります。
休業手当と有給休暇の違い|どちらを使うべき?
会社都合の休業が発生した場合、労働者は有給休暇を使用するか、休業手当を受け取るかを選択できます。ただし、会社から一方的に有給休暇の使用を強制することはできません。
| 項目 | 休業手当 | 有給休暇 |
| 支給額 | 平均賃金の60%以上 | 通常の賃金の100% |
| 有給日数 | 消費しない | 消費する |
| 労働者の選択 | 会社判断 | 労働者の権利 |
| 課税 | 課税対象 | 課税対象 |
有給休暇を使用すれば100%の賃金を受け取れますが、貴重な有給日数を消費することになります。一方、休業手当は60%の支給ですが、有給日数は温存できます。短期間の休業で、今後有給休暇を使う予定がある場合は、休業手当を受け取る方が有利な場合もあります。状況に応じて判断しましょう。
育児休業給付金・介護休業給付金との違い
育児休業給付金と介護休業給付金は、雇用保険から支給される給付金です。休業手当とは目的も財源も異なる制度です。
| 制度 | 対象 | 支給額 |
| 休業手当 | 会社都合の休業 | 平均賃金の60%以上 |
| 育児休業給付金 | 育児のための休業 | 休業開始時賃金の67%(180日経過後は50%) |
| 介護休業給付金 | 家族介護のための休業 | 休業開始時賃金の67% |
育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。育児休業中は社会保険料が免除されるため、実質的な手取り額は通常の給与とほぼ同水準となります。介護休業給付金は、家族の介護のために休業する場合に、通算93日を限度に支給されます。いずれも休業手当とは併給できません。
休業手当の支給期間|いつからいつまで?上限はある?
支給開始日|休業開始日から支給
休業手当の支給は、休業開始日から始まります。待期期間などはなく、会社都合で休業となった初日から休業手当を受け取る権利が発生します。
例えば、月曜日から休業が開始された場合、月曜日から休業手当の支給対象となります。実際の支払いは、通常の給与支払日に合わせて行われることが一般的です。会社が給与を月末締め、翌月25日払いとしている場合、その月の休業分は翌月25日に支払われます。
- 休業開始日から支給対象(待期期間なし)
- 実際の支払いは通常の給与支払日に行われることが多い
- 所定労働日のみが対象(土日祝日などの休日は含まれない)
- 一部休業(早退など)の場合も平均賃金の60%に満たなければ差額支給
支給期間の上限|法律上の制限はなし
労働基準法第26条には、休業手当の支給期間に関する上限の定めがありません。理論上は、会社都合の休業が続く限り、無期限に休業手当を支払い続ける義務があります。
ただし、長期間の休業が続く場合、実務上は以下のような対応が取られることが一般的です。
| 期間 | 一般的な対応 |
| 短期(数日~数週間) | 休業手当を支払い、業務再開を待つ |
| 中期(1~3か月) | 休業手当を継続し、雇用調整助成金の活用を検討 |
| 長期(3か月以上) | 整理解雇や希望退職の募集など、雇用調整を検討 |
2025年10月現在、長期間の休業が予想される場合、会社は雇用調整助成金などの公的支援制度を活用することで、休業手当の負担を軽減できます。労働者としても、休業が長期化する見込みの場合は、転職活動や職業訓練の受講なども検討する必要があるでしょう。
長期休業の場合の注意点
休業が長期化すると、様々な問題が発生する可能性があります。労働者として知っておくべき注意点は以下のとおりです。
- 収入減少:休業手当は平均賃金の60%のため、長期化すると生活への影響が大きい
- 社会保険料負担:休業中も社会保険料は通常どおり徴収されるため、手取り額がさらに減少
- 雇用不安:長期休業は解雇や事業閉鎖の前兆である可能性がある
- スキルの低下:長期間業務から離れることで、職業能力の維持が困難になる
- 再就職の困難:休業期間が長いと、転職活動において不利になる可能性がある
長期休業が予想される場合は、会社に対して今後の見通しを確認することが重要です。また、必要に応じて労働組合や労働基準監督署、弁護士などに相談することも検討しましょう。
休業が終了した場合の扱い
休業が終了し、通常の業務に復帰した場合、休業手当の支払いも終了します。通常の給与に戻り、休業期間中の不足分が追加で支払われることは原則としてありません。
ただし、以下のような場合は注意が必要です。
| 状況 | 取り扱い |
| 段階的な業務再開 | 時短勤務などで給与が平均賃金の60%未満の場合、差額分の休業手当が必要 |
| 一部の従業員のみ復帰 | 休業を継続する従業員には引き続き休業手当が必要 |
| 休業後の解雇 | 解雇予告手当の支払いが必要(平均賃金の30日分以上) |
休業終了の通知は、会社から明確に行われるべきです。曖昧な指示のままで業務に復帰した場合、後日賃金に関するトラブルが発生する可能性があるため、書面での確認を求めることをおすすめします。