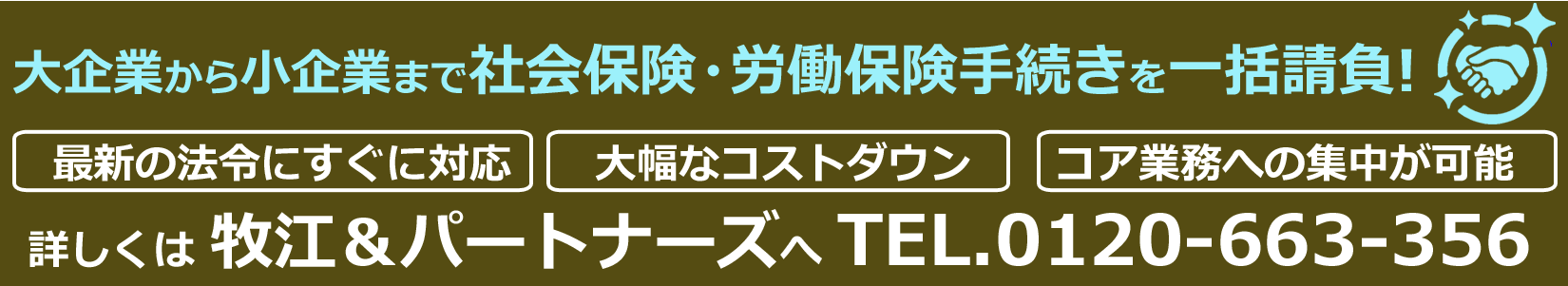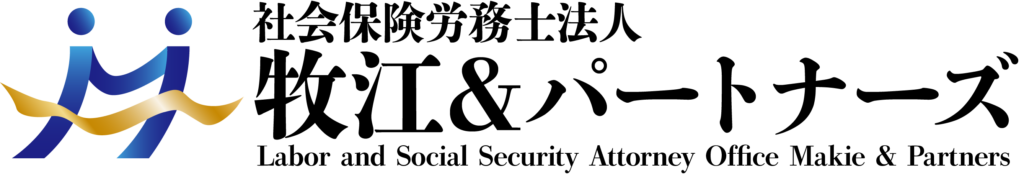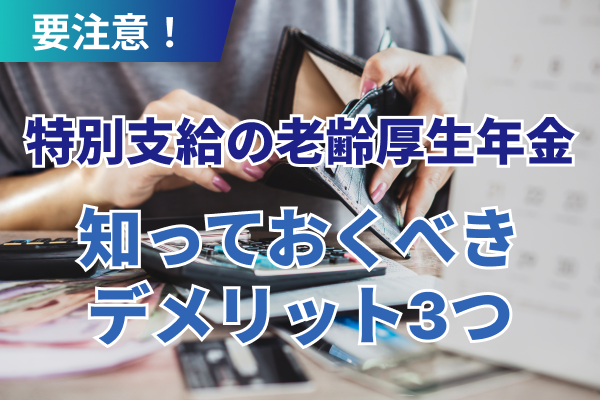
特別支給の老齢厚生年金は、60代前半に受け取れる年金制度ですが、実はデメリットも存在します。デメリットを知らずに受給を始めてしまうと、結果的に”損”をしてしまうこともあります。
この記事では、特別支給の老齢厚生年金の3つの主要なデメリットを詳しく解説し、もらえる人・もらえない人の条件、受け取るべきかどうかの判断基準まで、2025年最新の情報をもとに説明します。
- 特別支給の老齢厚生年金の3つのデメリット(減額・税負担・繰下げ不可)
- もらえる人・もらえない人の条件(生年月日で判定)
- 28万円・47万円の壁の計算方法と具体的なシミュレーション
- 税金・社会保険料の負担増の実態
- 受け取るべきか否かの判断基準
- 受給手続きの流れと注意点
そもそも特別支給の老齢厚生年金とは?【基礎知識】
特別支給の老齢厚生年金の3つのデメリットを理解するには、まず制度の基本を知ることが重要です。ここでは、特別支給の老齢厚生年金について基礎知識を解説します。
60歳から64歳まで(2025年度時点)の人が受け取れる、老齢厚生年金の早期支給版。以下の条件を満たす場合に受給できる。
- 男性の場合、昭和36年(1960年)4月1日以前に生まれたこと
- 女性の場合、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
60歳台前半に受け取れる年金制度
特別支給の老齢厚生年金(特老厚)とは、本来65歳から支給される老齢厚生年金を、60歳台前半から受け取れるようにした制度であり、段階的に廃止されることが決まっています。
平成6年(1994年)の法改正により、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。その急激な変化を避けるため、一定の生年月日以前に生まれた人に対して60歳台前半から受給できる経過措置が設けられました。これが「特別支給の老齢厚生年金」です。
支給開始年齢は生年月日により60〜64歳まで段階的に引き上げられており、最終的には男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた人は対象外となります。2025年10月現在、この制度の対象者は段階的に減少しており、将来的には完全に廃止される予定です。
もらえる人・もらえない人の条件(生年月日がすべて)
特別支給の老齢厚生年金をもらえるか否かは、生年月日によって完全に決まります。男性は昭和36年(1961年)4月1日以前生まれ、女性は昭和41年(1966年)4月1日以前生まれで、かつ厚生年金に1年以上加入していることが条件です。
| 生年月日(男性) | 支給開始 | 生年月日(女性) | 支給開始 |
| 昭和28年4月2日〜30年4月1日 | 60歳 | 昭和33年4月2日〜35年4月1日 | 60歳 |
| 昭和30年4月2日〜32年4月1日 | 61歳 | 昭和35年4月2日〜37年4月1日 | 61歳 |
| 昭和32年4月2日〜34年4月1日 | 62歳 | 昭和37年4月2日〜39年4月1日 | 62歳 |
| 昭和34年4月2日〜36年4月1日 | 63歳 | 昭和39年4月2日〜41年4月1日 | 63歳 |
| 昭和36年4月2日〜38年4月1日 | 64歳 | 昭和41年4月2日〜43年4月1日 | 64歳 |
| 昭和38年4月2日以降 | 対象外 | 昭和43年4月2日以降 | 対象外 |
参照:日本年金機構公式サイト
この表から分かるように、2025年10月現在、男性は61歳以上、女性は56歳以上でないと特別支給の対象にはなりません。自分が対象かどうかは、この表で生年月日を確認して判断しましょう。
女性の支給開始年齢引き上げは男性より5年遅く設定されています。これは、女性の平均余命が男性より長いことなどを考慮した措置です。
報酬比例部分と定額部分の違い
特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」で構成されていましたが、定額部分は段階的に廃止され、現在(2025年)受給している人は報酬比例部分のみとなっています。
当初の制度では、老齢基礎年金に相当する定額部分と、厚生年金独自の報酬比例部分の両方が支給されていましたが、平成13年(2001年)の改正により定額部分の支給開始年齢も段階的に引き上げられました。最終的には報酬比例部分のみが60歳台前半で支給される形となり、定額部分は65歳以降の老齢基礎年金として支給されるようになりました。
定額部分の支給開始年齢引き上げスケジュールは、男性は昭和16年4/2〜昭和24年4/1生まれが対象で、昭和24年4/2以降は定額部分なし、女性は昭和21年4/2〜昭和29年4/1が対象となっています。2025年10月現在、定額部分を受給できる人はほとんどおらず、実質的には報酬比例部分のみの支給となっています。
特別支給の老齢厚生年金の3つのデメリット
ここまでで解説した特別支給の老齢厚生年金には、知っておくべき3つのデメリットがあります。働きながら受給すると減額される「28万円の壁」、税金や社会保険料の負担が増えるケース、そして一度もらい始めると後から受け取り時期を遅らせて金額を増やすことができない、といったデメリットです。
ただし、デメリットがあるからといって必ずしも受給を避けるべきではありません。多くの人にはメリットの多い年金制度です。デメリットを正しく理解した上で、賢く活用しましょう。
デメリット1|在職中だと減額される(28万円・47万円の壁)
60歳以降も働きながら特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合、給与と年金の合計額が月額28万円(2025年度)を超えると、超えた額の2分の1が年金から減額されます。
-
10万円 + 25万円 = 35万円(28万円を7万円超える)
-
7万円 × 1/2 = 3.5万円(年金から差し引かれる金額)
これを「28万円の壁」と呼びます。
この減額制度は在職老齢年金制度に基づくもので、60〜64歳の年金受給者に一定以上の収入がある場合、年金額を調整する仕組みです。
高給与の場合は年金が全額停止されることもあり、働き方によっては実質的に年金を受け取れないケースもあります。65歳以降は基準額が47万円に引き上げられる(47万円の壁)ため、減額の影響は小さくなります。
デメリット2|税金・社会保険料の負担が増える
特別支給の老齢厚生年金は雑所得として課税対象となり、年金受給により所得が増えることで健康保険料や介護保険料の負担も増え、配偶者の扶養要件にも影響する可能性があります。
65歳未満の場合は年金収入108万円超、65歳以上は158万円超で所得税が発生します。また、国民健康保険料は所得に応じて計算されるため、年金を受け取ることで保険料負担が増加します。
- 所得税約1.2万円
- 住民税約2万円
- 国民健康保険料約8万円
→120万円 - (1.2万円 + 2万円 + 8万円) = 手取りは約109万円に
さらに、配偶者の健康保険の扶養に入っている場合、年金収入が年間180万円(60歳以上)を超えると扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入する必要があり、新たな保険料負担が発生します。
デメリット3|繰下げ受給ができない
特別支給の老齢厚生年金は、受給開始年齢を遅らせて年金額を増やすこと(繰下げ受給)ができません。
繰下げ受給制度は65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金(本来支給)のみを対象としています。特別支給の老齢厚生年金は、受給権発生から5年を経過すると時効により受給権が消滅します。請求を遅らせても増額はなく、むしろ損失となる可能性があります。
特別支給の老齢厚生年金はいくらもらえる?
特別支給の老齢厚生年金のデメリットを理解したら、実際にいくらもらえるのかを知っておきましょう。受給額は個人の加入履歴によって大きく異なります。
ここでは平均的な受給額、年収別のシミュレーション、そしてねんきん定期便での確認方法を詳しく解説します。
平均的な受給額の目安
特別支給の老齢厚生年金の平均的な受給額は、月額5万円〜10万円程度が一般的であり、厚生年金加入期間が長く、給与水準が高かった人ほど受給額は多くなります。
受給額は加入期間と平均給与で決まるため、個人差が大きくなります。厚生年金加入期間が20年で平均月収30万円の場合、おおむね月額6万円程度、加入期間35年で平均月収40万円の場合は月額12万円程度となる計算です。
厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、60〜64歳の老齢厚生年金受給者(特別支給含む)の平均月額は約9万円(2024年度)となっています。ただし、これは特別支給のみの額ではなく65歳以降も含むため参考値となります。実際の特別支給のみの平均額はこれよりやや低いと考えられます。
年収別のシミュレーション
計算式に基づき、具体的な年収パターンでシミュレーションすると以下となります。
①年収300万円(月額25万円)×30年→約25万円×5.769/1000×360月≒月額5.2万円
②年収500万円(月額42万円)×35年→約42万円×5.769/1000×420月≒月額10.2万円
③年収700万円(月額58万円)×40年→約58万円×5.769/1000×480月≒月額16万円
| 平均年収 | 加入期間 | 平均月収 | 受給額(月額) |
| 300万円 | 30年 | 25万円 | 約5.2万円 |
| 500万円 | 35年 | 42万円 | 約10.2万円 |
| 700万円 | 40年 | 58万円 | 約16万円 |
標準報酬月額の上限は65万円(2025年度)なので、高年収でも一定以上は反映されません。また、2003年3月以前の加入期間がある場合は、実際の受給額は個別に計算が必要です。
自分の正確な受給額を知りたい場合は、ねんきん定期便を確認するか、年金事務所で試算してもらうことをおすすめします。
ねんきん定期便での確認方法
日本年金機構から毎年誕生月に送付されるねんきん定期便には、将来受け取れる年金額の見込みが記載されています。
特別支給の対象者(昭和36年4月1日以前生まれの男性等)には、「●歳から受け取れる老齢厚生年金」として特別支給の金額が明示されます。50歳以上のねんきん定期便には、特別支給の受給開始年齢と年額が具体的に記載されているため、自分の受給額を正確に把握できます。
また、ねんきんネット(インターネットサービス)では、より詳細な試算も可能です。加入履歴の確認、将来の年金見込額の試算、繰下げ受給した場合の試算などができます。
ねんきんネットを利用するには、アクセスキー(ねんきん定期便に記載)またはマイナンバーカードが必要です。不明点がある場合は、年金事務所または「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165)に問い合わせることをおすすめします。
受け取るべき?受け取らない方が良い?【判断基準】
特別支給の老齢厚生年金のデメリットを理解しても、「受け取るべきか、受け取らない方がよいか」迷う人もいるでしょう。結論から言えば、ほとんどの場合は受給すべきですが、一部例外的なケースも存在します。
ここでは、受け取るべき人の特徴、受け取らない方が良いケースの有無、そして判断に迷ったときの相談先を詳しく解説します。
受け取るべき人の特徴
特別支給の老齢厚生年金は原則として受け取るべきです。特に、以下の特徴に当てはまる人は受け取ったほうがよいでしょう。
- 働いていない人
- 給与が低く減額の影響が少ない人
- 早期に資金が必要な人
特別支給は繰下げできず、請求を遅らせても増額しないため、受給権が発生したら速やかに請求することが合理的です。働いていない人は減額もなく、税負担も少ないため、受給しない理由はほとんどありません。給与が低い人(月15万円以下等)も減額の影響が小さいため、受給すべきです。
また、住宅ローンや教育費など資金需要がある場合も、早期受給が有利となります。時効により5年を超えた分は受け取れなくなるため、請求を遅らせることのデメリットは大きいといえます。
受け取らない方が良いケースはある?
特別支給の老齢厚生年金を「受け取らない方が良いケース」は、雇用保険の失業給付を受給する場合のみであり、それ以外で受け取らないメリットはほとんどありません。
雇用保険の基本手当(失業給付)と老齢厚生年金は併給できないため、失業給付を受ける期間中は年金が停止されます。失業給付の方が金額が多い場合は、年金の受給を一時的に見合わせることがあります。ただし、失業給付終了後は年金を受給できるため、「受け取らない」というより「一時停止」です。
基本手当受給中は特別支給が全額停止されます。基本手当の上限額(60〜64歳)は日額約7,200円(月約22万円)で、年金より多い場合は基本手当を優先します。ただし、基本手当の受給期間は最長150日(自己都合退職)または330日(会社都合退職)で終了するため、長期的には年金受給が有利です。失業給付を受給しない場合は、年金を請求すべきです。
判断に迷ったときの相談先
特別支給の老齢厚生年金の受給に関する相談は、最寄りの年金事務所、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)、または社会保険労務士に問い合わせることで、個別の状況に応じた適切なアドバイスを受けられます。
年金制度は複雑で個人の状況により最適な選択が異なるため、専門家に相談することが重要です。年金事務所では、年金記録の確認、受給額の試算、手続き方法の案内などを無料で受けられます。社会保険労務士は有料ですが、より詳細なライフプラン相談も可能です。
年金事務所での相談は予約制が推奨されています(混雑緩和のため)。ねんきんネットで自分の年金記録を確認し、簡易試算も可能です。社会保険労務士会の無料相談会も定期的に開催されています。判断に迷った場合は、複数の相談先で情報を集め、自分の状況に最適な選択をすることをおすすめします。
特別支給の老齢厚生年金の受給手続き
特別支給の老齢厚生年金を受給すると決めたら、次は手続きです。手続きは複雑そうに見えますが、日本年金機構から送付される請求書に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出するだけで完了します。
ここでは、請求手続きの流れ、必要書類、請求期限と時効、そして繰上げ受給との違いを詳しく解説します。スムーズに手続きを進めるための情報を網羅的に提供します。
請求手続きの流れ
特別支給の老齢厚生年金の請求手続きは、受給開始年齢到達の3か月前に日本年金機構から送付される「年金請求書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して年金事務所または年金相談センターに提出します。
日本年金機構は、特別支給の対象者に対して、受給開始年齢到達の3か月前に予め本人情報が印字された年金請求書を送付します。これにより、記入の手間が軽減され、手続きがスムーズになります。請求書提出後、約1〜2か月で年金証書が届き、その翌月または翌々月から年金が振り込まれます。
請求書には、氏名・生年月日・住所・年金加入記録などが予め印字されています。年金は偶数月の15日に、前2か月分がまとめて振り込まれます(例:2月15日に12月分・1月分を受給)。請求書が届かない場合や、紛失した場合は、年金事務所で再発行を依頼できます。
必要書類一覧
特別支給の老齢厚生年金の請求には、以下6つの書類が必要です。
- 年金請求書(日本年金機構から送付される)
- 戸籍謄本または住民票(請求日から6か月以内のもの)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預金通帳のコピー(本人名義)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 配偶者がいる場合:配偶者の戸籍謄本、所得証明書等(加給年金請求時)
年金請求には本人確認と年金記録の照合が必要なため、各種証明書類の提出が求められます。マイナンバーを記入する場合は一部書類が省略可能です。
配偶者がいる場合は、将来の加給年金請求に備えて配偶者の戸籍謄本や所得証明書も必要になることがあります。ただし、特別支給では原則加給年金はつかないため、多くの場合は基本書類のみで十分です。
戸籍謄本は請求日から6か月以内のものが必要です。配偶者の加給年金を請求する場合は、配偶者の年収が850万円未満であることを証明する所得証明書等が必要となりますが、特別支給では原則加給年金はつかないため、多くの場合は不要です。
請求期限と時効(5年)
特別支給の老齢厚生年金に請求期限はありませんが、受給権発生から5年を経過すると時効により古い分から受給権が消滅するため、受給開始年齢に達したら速やかに請求しましょう。
厚生年金保険法第102条により、年金給付を受ける権利は5年間行使しないと時効消滅します。請求が遅れても5年以内であれば遡って受給できますが、5年を超えた分は永久に受け取れなくなります。
時効の起算日は受給権発生日(誕生日の前日)です。例えば、60歳誕生日が2024年4月10日の場合、2024年4月9日が受給権発生日となり、2029年4月9日以降に請求すると、2024年4月9日〜2029年4月8日の5年分のみ受給可能(それ以前は時効)となります。
請求を忘れていた場合でも、5年以内であれば遡及受給できるため、気づいたらすぐに手続きすることが重要です。